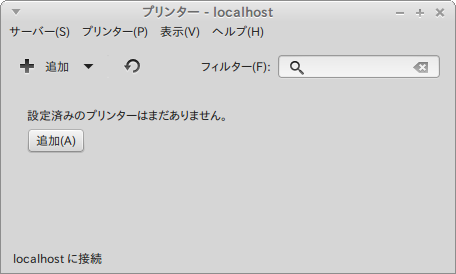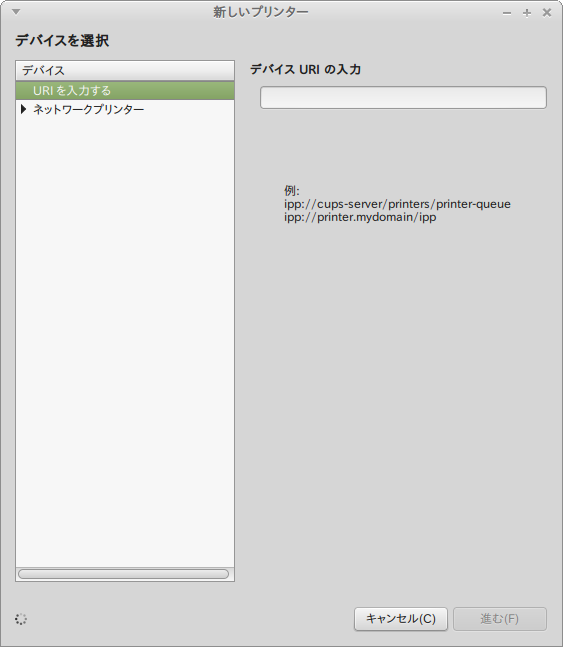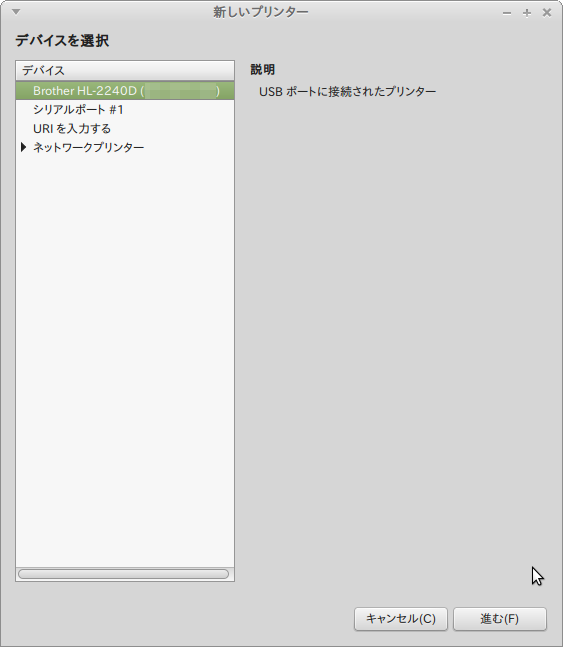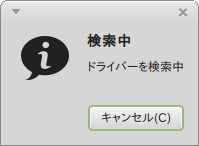再びUSBメモリのLinuxMintとLubuntuをインストールしてみました。
LinuxMintの方はLinuxMint17を16GBのSanDiskの小さな16GBのUSBメモリに、Lubuntuの方は同じく8GBのUSBメモリにインストールしました。
1.インストール
インストール自体は難しくありません。
- それぞれISOイメージをダウンロードしてDVD/CDROMを作成
- デスクトップPCでSATAを禁止してHDDを見えない状態にしてから、USB-CDROMでインストーラ起動
- USBメモリを挿入して手動でパーティション作成
手動でパーティション作成するのはPCの搭載メモリが多いのでSWAP領域が大きくとられてしまう対策です。 - あとは普通にインストール
2.チューニング
1)USBメモリへのアクセス速度向上のため、/etc/fstab を修正
ルートファイルシステムのオプションに「noatime」を追加して、アクセスタイムの記録をやめさせます。また、tmpfsを追加して、テンポラリファイルの書き込みをやめさせます。
2)起動後に内蔵HDDを見えないようにする
起動時のカーネルパラメータでlibataを禁止して内蔵HDDを見えないようにします。
/etc/defaults/grub を開いて、 「GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT」の起動時オプションに「libata.force=disable」を追加します。ついでに同じ箇所のオプションの「quiet」を取って起動時のメッセージを表示させるようにしました。
修正後は、
$ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
としてgrub.cfgファイルを自動生成させて反映させます。
この後、BIOSのSATA禁止を解除して再起動して、PCの内蔵HDDが見えないことを確認します。
3)ひたすらアップデートをインストール
大量のアップデートがあるので、ひたすら適用していきます。
4)アプリケーションのインストール
- Google Chrome
- clamtk
- その他、必要なアプリケーション
5)その他の設定
- システム時計が狂うのを直す
/etc/defaults/rcS の中の「UTC=yes」を「UTC=no」に修正
こんなところでしょうか。カーネルパラメータで指定するだけでSATAを禁止できるので、カーネルのバージョンアップなどがあってもカーネル再構築などをせずに済むので楽ちん(のはず)です。